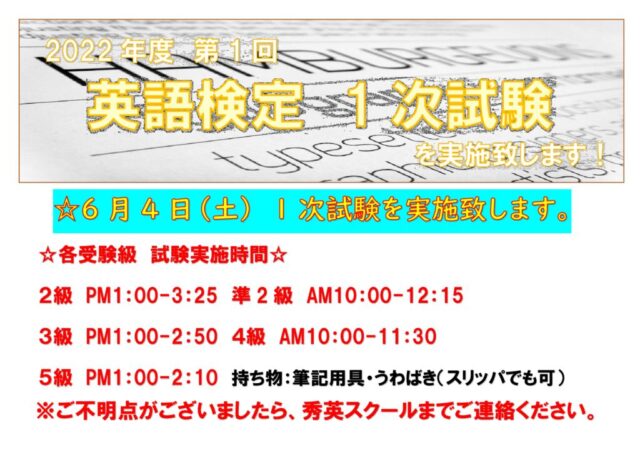最新の高校入試の情報をまとめます!
4月末に、今年2月に実施された、公立高校入試の受験者全体の平均点が発表されました!

☆ 今年の公立入試から言える受験生の皆さんへのアドバイス ☆
◎平均点が軒並み低下。今年の試験に向けても注目!
注目点① 「国語」の平均点が低下したとはいえ、高い状態! ミスしたら終わりの時代へ!
注目点② 「数学」と「英語」は取れる問題を絶対に落とさない! 間違えた問題は必ず復習を!
注目点③ 理科と社会は、平均点低下=問題が難しく。暗記+説明までできるよう、万全の準備を!
国語は平均点 60 点以上が、2年間続いています。必ず試験で「最初の科目」となりますので、他の科目のためにも、失敗が許されない科目となりつつあります。文章読解・漢字の読み書き・作文を軸に点数が取れるようにしっかり演習することで、「失敗しない科目」にすることが受験生の命題になります。
英語では「長文読解」と「英作文」でいかに点数を確保するかが重要になってきます。ここでの点数確保は受験勉強としてはずせません。学校選択でも学力検査でも、平均点が 50 点台ですが、受験生の開示得点を見ると、県難関校の「浦和」「大宮」「川越」では平均点が 70 点台~80点台が普通です。所沢北・熊谷でも 60 点半ばが平均点と言われる中で、しっかり得点を取ることが合格に近づくとも言えます。
数学では、中学 1 年生から中学 3 年生までの様々な単元の問題が総合して出題されています。学力検査問題では大問1が 65 点の計算・1行問題がメインになっています。ここで点数を稼ぐことが絶対的に必要です。そのためには夏までの時間で、中学 1 年・2 年生の範囲の計算・1行問題を繰り返し、復習することで確実に得点できるようにしましょう。また、注意してもらいたいものもあります。学校選択問題では、必出の「2次関数」「相似」「三平方の定理」が問題で多用されています。そういった問題を確実に攻略するためには、「単元ごとの反復練習をいかに行うか」が問題を解くカギとなりますので、今のうちから習慣づける良いでしょう。
最後に公立入試の理科・社会の点数に見られる内容になります。県難関校の「浦和」「大宮」「川越」を受験した生徒の開示点数を見てみると、約 85 点~90 点前半をとっている生徒が多いことが分かりました。所沢北・熊谷でも 80 点~85 点を取る生徒多く見られます。埼玉県の理科・社会は、教科書の基本内容がしっかり出題され、それをいかに適切に答えるかが、高得点のカギにもなっています。またこれは、公立高校入試全体にも言えることです。教科書に掲載されている内容をしっかり答えられるように、中 1・中 2 のうちから知識を養っていくことが公立入試で点数をとるための方法ということを理解しましょう。